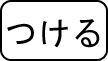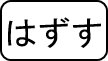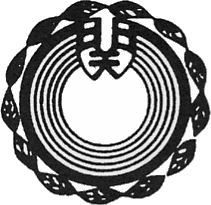令和7年度研究(主体的に取り組む児童の育成)
≪研修の概要≫
本校では、「主体的に取り組む児童の育成」を目指し研究を進めています。今年度は、教員も一人一人自分のやりたいことを決め、3つのチームに分かれて研究を進めています。
チームは、学習の基盤となる資質・能力「言語能力チーム」「情報活用能力チーム」「問題発見・課題解決能力チーム」に分かれています。どんな取り組みができるかを考え、教員同士で話し合って研究を進めています。
≪講師の先生方からのご指導≫
1学期間には、東京学芸大学教職大学院・教授 堀田 龍也先生、文部科学省教科調査官、加固 希支男先生、教科書研究センター 東京学芸大学教授 西村 圭一先生からご指導いただきました。
|
堀田先生 (ICTの活用などについて) ・教員は、明確な意図をもって指導することが大切。 ・指示は視覚化し、順序をつけて行う。 ・ICTは安心して学ぶために使用する。学びやすくするための学習基盤。 ・教科を通してもっと大きな能力や基礎を教えている。 ・紙とデジタルのそれぞれのよさを指導してから選択させることが大切。指導する側が、それぞれのよさをしっかりと理解しておくことが必要。 |
|
加固先生 (算数の指導について) ・単元のゴールでどのような資質、能力を育てていくかを考えて見通しをもって指導していく。 ・全ての児童に「主体的で対話的で深い学び」の実現を通して、資質能力の育成を図ることができるのかということを考え、授業を計画することが必要。 ・単元を通して働かせる大切な着眼点を見つけることが大切。(単元で大切な着眼点をクラウドなどで共有する。 過去の学習とのつながりも意識することができる。) ・様々な考えの中に、共通点を見付け、統合的に考えることが大切。統合・発展を繰り返していく。 |
|
西村先生 (教科書の使用の仕方について) ・児童の目線での教科書の使い方を考えることが大切。 ・教科書の見せ方を教科書のメリット、デメリットを教員側が把握し、よいタイミングで示していくことが必要になっていく。 ・教科書とノートとの連動。児童が考えた跡が、ノートに残ると良い。 |
↓ 西村先生のご講話ときの様子
1学期を通して得た学びを、これからの実践に生かし、子どもたちの学びへと返していけるよう努めていきます。
≪研究授業≫
更新日:2025年11月27日 07:28:10